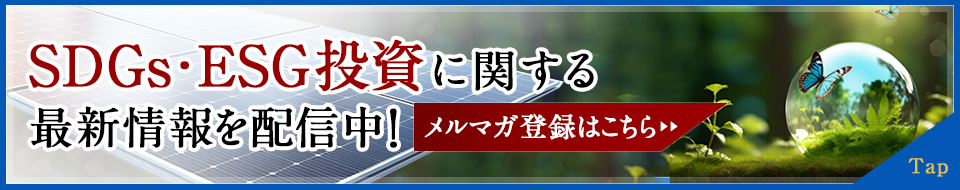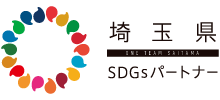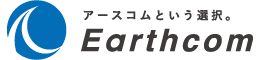2024.01.28
高所得のサラリーマンが節税するなら?おすすめの節税方法を解説
いつも当コラムをお読みいただき、ありがとうございます。
株式会社アースコム、取締役副社長の丸林です。
サラリーマンで高所得の場合、日本では累進課税制度が取られているため、所得が上がれば上がるほど税金が取られてしまいますよね。そのため、日ごろからどのような節税方法があるのかを把握しておくことが大切です。
正しい知識があれば、不要な出費を抑えつつ手元に残るお金を増やすことにつながるでしょう。
手元に残るお金を増やすためには、「節税」をしましょう!
今回は、高所得サラリーマンにおすすめの節税方法について解説!
どのくらいの金額が節税できるのか、副業などを利用して節税する方法にはどんなものがあるか、といった疑問にお答えします。

目次
高所得なサラリーマン向け節税対策!その方法や節税できる金額の目安
高所得になるほど税率が高くなる累進課税制度ですが、収入から経費や控除を差し引いた課税所得金額が901万円を超えると1,799.9万円までは税率が33%となります。
さらにプラスして住民税の10%がかかるため、税率は合計で43%となるのです。
また、配偶者控除についても所得が901万円以上になると控除額が減っていきます。
このように900万円を超える収入のあるサラリーマンにとっては、税額が非常に高額となり、頑張って収入を伸ばしても、多くが税金に取られるといった状況になります。
ここでは少しでも手取り収入を伸ばすため、おすすめの節税対策を紹介していきます。
ふるさと納税
ふるさと納税では、寄付金控除を受けることができます。
ふるさと納税は全国の自治体から寄付先を自由に選んで寄付を行い、寄付金の返礼として自治体の特産品などがもらえる仕組みです(返礼無しで寄付のみ行うものもあります)。
実質2,000円ほどの自己負担で寄附先の特産品がお礼品として受け取れるため、税金の使い道を明確にできる点や地域貢献の面でも注目されています。
所得税と住民税から還付されます。
控除額は、扶養家族の人数や住宅ローン控除額によって異なります。
ふるさと納税を扱うホームページでも、シミュレーションができますよ。
ふるさと納税は1月1日から12月31日までの寄付金に対して翌年控除されますので、年末までに控除額の上限まで寄付するのがポイントです。
また、高所得者ほど控除上限が高くなるため、より高額の寄附を行って節税メリットを得やすいのが特徴ですね。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金、iDeCo(イデコ)とは私的年金の一つです。
毎月、設定した金額を積み立てていき、掛金は自身で決めたポートフォリオに沿って運用されます。
サラリーマンの場合、掛金の上限はひと月あたり23,000円です。
iDeCoは掛金全額が所得控除となり、所得税と住民税の節税につながります。
また、iDeCoで運用して出た利益は非課税となるのもポイントです。
年金の一種なので積み立てた資産は原則として60歳以降に受け取る形になりますが、将来の老後資金作りと同時に現在の税負担も軽減できる点が魅力といえます。
年収1,000万円の方であれば、年間約83,000円(所得税と住民税の合計を30%として算出)の節税になります。
特定支出控除
サラリーマンは通常、業務にかかる支出を経費として落とせませんが、特定支出控除を利用すれば新聞図書費や交際費、資格取得費用、通勤費用などを一部経費として計上できます。
ただし、特定支出控除を使うためには以下の条件を満たす必要があります。
- 経費の合計額が給与所得控除の半分を超えること
- 特定支出控除を受けるための証明書を雇用先から発行してもらうこと
年収1,000万円の方の給与所得控除は195万円なので、経費の合計は98万円以上であることが前提です。
医療費控除
医療費控除は、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超える場合に確定申告をすると控除が受けられます。
配偶者や子どもなどの医療費の合算が可能です。
年収1,000万円の方の場合、計算方法は「実際に支払った金額-保険金などで補填される金額-10万円」で、最高200万円までが対象です。
年収1,000万円の方の場合、控除対象額が10万円だとすると、10万円×23%(所得税率)で、還付額は23,000円です。
計算に適用する所得税率が異なるため、所得が高いほど還付額は大きくなります。
そのため、家族で医療費控除を受ける場合は、家庭内で最も所得が高い人が医療費控除をしましょう。
セルフメディケーション税制
医療費控除では、健診や予防に関する費用は控除の対象外です。
「セルフメディケーション税制」は、健康維持増進や病気予防のための自主服薬が適用となり、確定申告をすると最大8万8,000円を限度額として控除が受けられます。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可なので、より節税効果の高い方を選ぶ必要があります。
セルフメディケーション税制を適用できるのは、以下の条件をいずれも満たす場合です。
- 厚生労働省指定の「スイッチOTC医薬品」を年間で12,000円以上購入している
- 定期検診や予防接種など健康の保持増進・疾病予防に取り組んでいる
配偶者控除
配偶者の収入が一定水準以下の場合に適用できる控除制度です。
控除対象となるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除が受けられません。
配偶者の所得が48万円を超えてしまった場合には、以下の条件を両方満たすときに、配偶者特別控除が受けられます。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
扶養控除
扶養親族(子どもや親など)がいる場合に適用できる控除制度で、その年齢や人数によって所得額からの控除額が変わります。
扶養親族の対象となるのは以下の条件をすべて満たす場合です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
生命保険料控除
生命保険、介護保険、医療保険、学資保険などに加入している場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
生命保険料控除は、2012年1月1日以後に契約した「新契約」と2011年12月31日以前に契約した「旧契約」の2区分に分かれます。
<新契約>※2012年1月1日以後に契約
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
<旧契約>※2011年12月31日以前に契約
| 年間の支払い保険料 | 控除額 |
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
両方契約している場合はそれぞれで計算した控除額を合算し、3区分合計で120,000円まで控除可能となります。
地震保険料控除
地震保険の保険料や掛金を支払った場合に、一定額の所得控除が受けられます。
控除額は、以下の通りです。
- 年間支払保険料が50,000円以下の場合、支払金額の全額
- 年間支払保険料が50,000円を超える場合、一律50,000円
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除は「住宅ローン減税」とも呼ばれる所得税控除です。
借入期間10年以上の住宅ローンを組んで、一定の住宅を購入・新築・増改築を行なった場合、年末のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税が控除されます。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除されます。
※令和4年度(2022年度)税制改正後
住宅ローン控除を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 省エネ基準に適合した住宅であること(※2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合)
- 省エネ基準以上適合の証明書を保有していること
- 新築又は取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き住んでいること
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 床面積が50平方メートル以上(※2023年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40平方メートル以上)
- ローン返済期間が10年以上であること
- 長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと
- 中古住宅の場合は1982年以降に建築又は現行の耐震基準に適合していること
新NISA
2024年から開始となる新NISAも節税となります。
通常、株や投資信託の売買を行なって出た利益については、20.315%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引で出た利益については、全て非課税となります。
旧NISAやつみたてNISAは、非課税期間に上限がありましたが、新NISAについては、この非課税期間の上限が撤廃され、無期限で非課税となります。
新NISA内のつみたて枠で年間120万円まで、成長投資枠で年間240万円、最大で年間360万円までの投資で得られた利益が非課税になります。
非課税対象となる保有限度枠は1,800万円までとなり、旧NISAやつみたてNISAと比べても大きく投資ができるようになりました。
不動産投資・太陽光発電投資
不動産投資や太陽光発電投資を行い、減価償却費を本業の年収と合算して、見かけ上の赤字を作ることで課税所得額を減らす方法です。
不動産投資や太陽光発電に投資した費用は、会計上数年に分けて減価償却費として計上します。
家賃収入や売電収入から減価償却費や維持費などの費用を差し引いた金額が赤字となり、サラリーマンであれば、給与収入と赤字額を損益通算(相殺)することが可能です。
損益通算することで、見かけの収入が低くなるため税金が下がります。
減価償却費は、あくまでも会計上のものであり、キャッシュで支払うわけではありません。
毎年のキャッシュフローとしてはプラスとなるのです。
詳しい仕組みについては、それぞれ以下のコラムをご覧ください。
【まとめ】太陽光発電でできる節税対策とは?メリットや節税対策を振り返ろう
特定の事情がある場合に適用できる節税方法
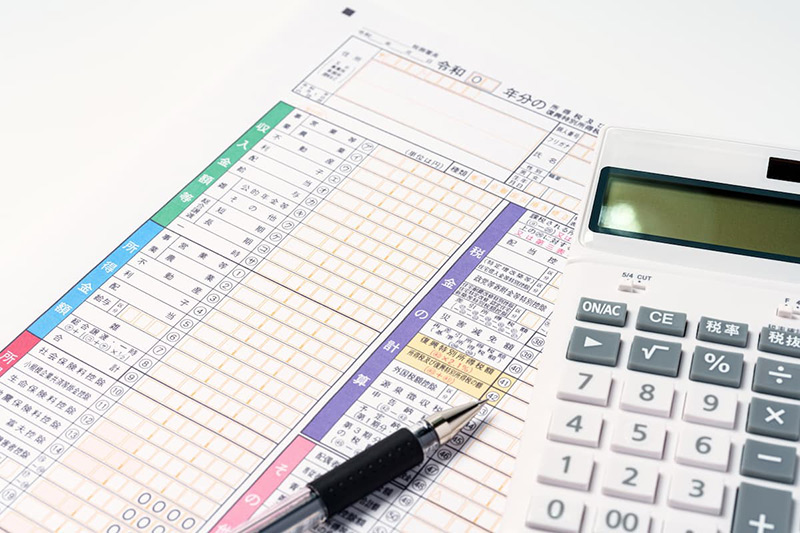
以下で説明する節税方法は、特定の事情に該当した場合の節税方法です。
該当する事象が発生した場合は、対応できるように確認しておきましょう。
株取引で損出を出した場合
現物株の取引や投資信託などの金融商品の取引で損出を出した場合、翌年から3年間に渡って、その年の利益と損出分を相殺できます。
損出が大きく、その年の収支ではマイナスになってしまう場合は、「繰越控除」という仕組みを使って損失を繰越し、3年間のうちに利益が出れば、その利益分と相殺できるので税額が抑えられます。
ただし、先程紹介した新NISAでは、繰越控除は適用されませんので注意が必要です。
繰越控除を使うには、控除する3年間、毎年確定申告を行わなければなりません。
災害や盗難にあった場合
雑損控除や災害減免法は災害や盗難、横領などの不可抗力によって自分の資産に損害を受けた場合に控除が受けられます。
ただし、詐欺や恐喝の場合は「自分が渡した」という一面があるため、雑損控除が受けられません。
配偶者と離婚または死別した場合
配偶者と離婚または死別した場合、寡婦控除やひとり親控除の対象となる可能性があります。
生計を一にする子がいること、合計所得所得金額が500万円以下など一定の条件がありますので、条件に該当している場合は年末調整で申請できます。
サラリーマンで高所得なら個人事業主として副業・会社設立で節税も

サラリーマンで高所得の場合、副業をして個人事業主になるか、資産管理会社を設立するのも節税対策として効果が高くおすすめです。
個人事業主になり経費計上する
副業は個人事業主にならなくてもできますが、ただの副業だと経費を計上できません。
そこで、開業して個人事業主となることで仕事にかかる諸費用を経費として計上でき、課税所得額を減らすことができるのです。
青色申告をすれば控除額が増えて節税効果がアップしますので、開業届とあわせて青色申告の申請も行いましょう。
個人事業主・青色申告についてはこちらもあわせてご覧ください。
太陽光発電で節税するなら個人事業主がお得!青色申告で節税しよう!
法人として会社を設立する
年収が3,000万円を超える方であれば、自分の資産を管理する目的で資産管理会社を設立する方法があります。
会社を設立する目的の一つは、個人事業主のケースと同じように仕事にかかる諸費用を経費化できることです。
2つ目は、所得税率よりも低い法人税率を適用できること。
所得税は、1,800万円を超え4,000万円以下の部分には税率40%がかかりますが、法人税は最高でも23.2%です。
法人であれば家族への給料も経費にできるので、節税できる範囲が広くなります。
高所得のサラリーマンほど節税対策を!
累進課税制度がある日本では、所得が高くなればなるほど、高い所得税率がかかってきます。
手元により多くのお金が残るよう、課税所得額が減らせる控除や、所得控除を利用しましょう。
控除だけでは限界があるため、不動産投資や太陽光発電投資などの減価償却費を利用する方法は、節税効果も高くおすすめです。
特に年収が高いサラリーマンは、開業して個人事業主になるか、法人を設立する方法もあります。
諸費用が経費として計上でき、利益圧縮につながるほか、法人化すれば高い所得税率よりも低い法人税率を適用可能です。
アースコムでは、環境や社会に優しく、事業としても収益を上げていく、太陽光発電投資・環境事業投資をサポートしています。
節税対策に利用したい方は、お気軽にご相談ください!